|
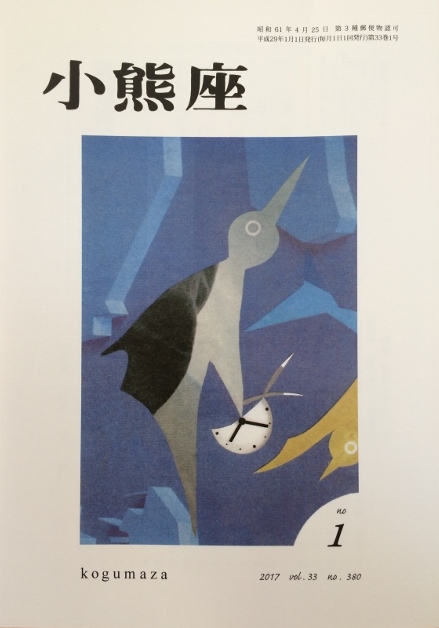
|
 2017/10 №389 小熊座の好句 高野ムツオ 2017/10 №389 小熊座の好句 高野ムツオ
送り火の消えて茗荷の花あかり 阿部 菁女
「送り火」と「茗荷の花」は、どちらも秋の季語である。一般的に季重なりは主題が
二つ以上重なることになるので忌避する。これは明治になって季題という言葉が生ま
れ、虚子が「俳句は季題を詠ずる文学なり」と主張してから広まったことのようだ。蕉
門俳諧では、季重なりをむしろ積極的に許容しようとする傾向もあったと、浅沼璞は
「現代俳句ハンドブック」で述べている。実際、芭蕉に季重なりの句は多いが、季題を
重んじた虚子にもかなりある。肝要なのは季語がそれぞれの情趣を妨げたり重複し
たりせず、一句の中で生きて働いているかどうかということであろう。ただし、季重なり
の句を多作した俳人の一人飯田龍太が、それでも一句に季語一つと定めて作句す
るのは大切な修練と述べていたことは付け加えておきたい。
この句には、他にも問題となる言葉づかいがある。「花あかり」である。単独では、
夜桜のほの明るさを示す季語で、雪明かりと同じように夜にあっての明るさを意味す
る。ここでは茗荷の花として造語的に用いた。成功しているが濫用すべきではない。
ことに昼の明るさとして使うべきではないだろう。ここでは門火を終えたのち、ふと畠
隅にでも見つけた茗荷の花として鑑賞したい。淡黄色の花が、闇に慣れた眼に、あ
の世から戻ってきた誰彼の姿に重なったのである。どこかに幼子のイメージを誘うと
ころが、いっそう作者の思いを深くする。消えたばかりの送り火の残像でもある。蛇足
だが、茗荷の花はショウガ科ショウガ属の多年草の花のこと。若芽は茗荷竹と呼び
春の季語。晩夏の花穂は茗荷の子と呼ぶ。薬味など食用とするのは、この時期のも
のだ。花茗荷は別属のショウガ科ハナミョウガ属の常緑多年草のこと。夏の季語で
混同を避けたい。
苦瓜に百の涙状突起あり 我妻 民雄
「涙状」は聞き慣れない言葉で、これも造語だろう。なるほど苦瓜の表面を覆ってい
る疣状の突起は確かに眼から噴き出した涙のようにも見える。ゴーヤーは苦瓜の沖
縄名で、昨今はこちらの方が膾炙されている。もうこの句の言わんとすることは説明
するまでもないだろう。あのツブツブは琉球と呼ばれた頃からの、この列島の苦難の
涙そのものなのである。造語力は日本語の特質の一つだが、安易な使用は禁物で
ある。
涙いまかわく途中や草かげろう 沢木 美子
いつ、どこで流した涙なのだろうか。一般的には、こうした曖昧さは欠点となるのだ
が、ここでは、むしろ、さまざまに想像を広げる効果をもたらしている。人間は生まれ
た時から泣く。幼時、少年少女時代、そして、青年時代にもさまざまな涙を流す。父母
との別れにも涙はあふれる。うれし涙をこぼした時もあろう。人それぞれ、涙はいつも
つきものだったに違いない。しかし、その涙も必ず乾く時が来る。それは、自分自身
がこの世と別れる時である。「乾く途中」とは、その瞬間がそのうち訪れるという、自ら
の一生を見つめる醒めた意識が生んだ言葉である。クサカゲロウはカゲロウよりは
長生きだが、その緑色の姿態はカゲロウとはまた別趣のはかなさを帯びる。
夏蝶が囁く海へ行つて来ます 関根 かな
背後からやって来ては翻って消えたキアゲハであろう。耳元を過ぎっては海の方向
に飛び去る鮮やかな姿態が見えてきそうだ。エネルギッシュな躍動感に満ちた句と読
んでも魅力的だが、「囁く」は誘いの言葉でもある。海になかなか足を運べない作者
に、分身としてのアゲハが呼びかけているかのようにも鑑賞できる。すると、大津波
以後、海と向き合うことのできない作者が次第に見えてくる。揚羽には蝶道といって
一定の飛ぶルートがあるらしい。毎日同じ時間に同じ場所を飛ぶともいわれている。
特に雄に見られる行動のようだ。津波のため生まれ得ずして亡くなった無数の蝶へと
生き残された蝶が会いに行く。その囁きだと読むのは鑑賞過剰だろうか。
蛍より阿弖流為の闇始まりぬ 中村 春
一読、金子兜太の〈おおかみに蛍が一つ付いていた〉を想起した。狼も蛍も滅びいく
ものの象徴である。その光の後ろに、さらに千年以上前に滅んだ阿弖流為のみちの
くの闇が広がっているのである。
神が鈴振れば鉄漿蜻蛉舞ふ 水戸 勇喜
糸蜻蛉の類を神様蜻蛉と呼ぶ地方もあるようだが、ここでは黑い翅のハグロトンボ
であろう。「羽黒」と「歯黑」を重ねた呼称である。ひらひらと舞い飛ぶ様に巫女の姿を
連想したのだ。巫女装束は白小袖に緋袴と相場が決まっているが、神式の葬では鈍
色の装束も身につけることがあると知った。それなら、これは鎮魂の舞ということにな
る。
夜濯ぎの渦や漂泊銀河まで 吉野 和夫
他界にも星は生まれて稲の花 佐藤 みね
|
パソコン上表記出来ない文字は書き換えています
copyright(C) kogumaza All rights reserved
|
|